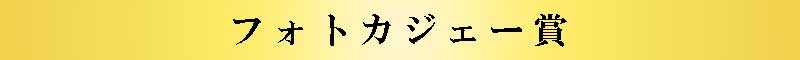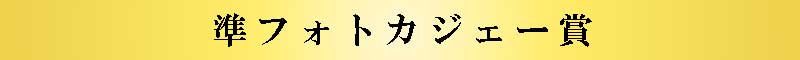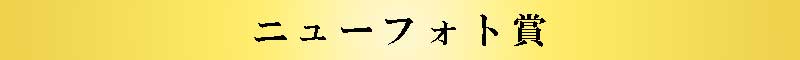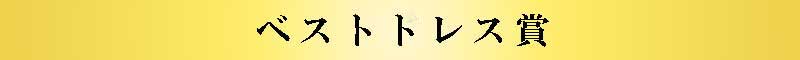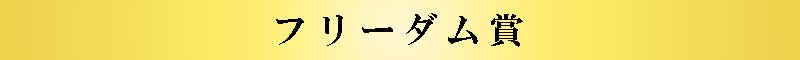病院でしょうか、そこで過ごされる年老いたお母さんとご長男との面会の一コマです。
なんのてらいもない、実に素朴な写真でありながら、人の世の幸せのありがたさとせつなささえも伝わってきます。
作者の被写体との距離、レンズの画角、立ち位置の適切な選択また、逆光気味の光によって、お二人が平板にならず、リング状のゴーストさえもが写真に動きとリズムをかもしだし、生き生きと笑い声までが聞こえてきます。
このことは、作者がおそらく年月をかけて写真を愛し愛され、寫眞機そのものが身体の一部に成っているからではと思います。
写真を見ていて感心しましたのは、単なるスナップ写真で終わらずに、このお二人は私達にとって決して見知らぬ他者ではなく、同じ時代を生きる隣人として共感させてくれるからです。
改めて人と正面から向かい合う写真の力を見せてくれました。
家族の記念写真は写真の一番の原点ですが、この作品は記念写真にとどまらず記録と表現とを兼ね備えた優れたヒューマンドキュメントの作品になっています。
お二人のご家族にとって大切な宝物となって生き続けるに違いありません。
正直、なにも付け加えるものはありません、まさに眼福そのものです。
【評:平井純】
木の枝に二羽の鳩、柔らかい首を伸ばして求愛するオス。なぜかぎこちない。観察して思った。
腕を空飛ぶ翼に変えてしまったから人間のように抱擁が出来ないのだ。にも拘らず、微笑ましく感じる。
タイトルにある「季節」が人間との対比で面白い。人間には何時の求愛はあっても「恋の季節」はないように思える。
鳩は巡る季節の中でこの時期にだけ「恋の季節」が訪れる。背景の黄緑色がその季節感を見事に表現している。
私だけかもしれないが、複雑に進化する人間愛の現代にあって、シンプルにめぐり合う季節の愛も好いのではないだろうか。
作者の思いは未聞だが、鳩の求愛を擬人化し想像力を勝手に膨らませる作品は何度見ても飽きる事はない。作者の豊かな想像力に乾杯したい。
【評:奥村よしひろ】
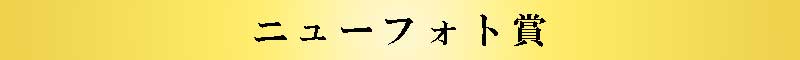
一瞬この美しい写真を見てタイトルが“マイウエイ”と言うのがとても奇異に思われましたが、よく見ると1羽の鴨が主人公であることが分かります。
群れから離れた1羽の鴨が、静かにさざ波の立つ湖面に映し出された白樺の林の中を、問答無用と言わんばかりに林を切り裂く様子を見事に捉えておりますし、林の白い木立と紅葉の色のバランスが素敵です。
風景写真は、よく運との出会いであると言われますがますが、まさに季節や天気や時間によって変化する自然の中での瞬間 的な出会いが、このような感動的な写真を生むのでしょう。
お洒落な“マイウエイ”はまさにニューフォト賞に相応しい作品です。
【評:坂本阡弘】
命を終えた水面に浮かぶトンボ、死者と成ったトンボの姿、そしてトンボの側のミズスマシのいる光景。この三枚の写真で「水葬 生と死」という心象的な作品が構成されています。
作品は水色一色のモノクロームの色調で統一されたことで作品の底奏音となって生と死のイメージが喚起されるコンセプチャルな作品となりました。
少し深読見しますと、ミズスマシはトンボによりそう野辺の送りとも読めます。改めて写真を見つめますと、少し気になるところがあります。写真は写真に語らせるものでなく、写真自らが語るものです。
作者は難しいテーマ故に写真に語らせてしまったところが惜しいです。この作品にはテーマを深める大事なモチーフが幾つも潜んでいますので生かしてください。
例えばテーマでもある一回性という、二度と同じものはおきない水面の波紋や変わることの無い水面に映える太陽の光や透明感のあるトンボの羽などをしっかりと視覚化することで、作品の厚みや深さが生まれ、見るものの想像力をかきたててくれます。
その意味で、同じモノトーンでも象徴的な表現のできる白と黒とのほうが、この作品には向いているのではと思います。
光は闇の中でこそ輝きます。トンボそのものを凝視することこそ、メメント、モリ、死を想えであり、祈りと再生の表現につながっていきます。遺影となったトンボそのものである左右の羽の先が欠けてしまったのももったいないです。参考に色々と試してください。
作者の祈りの写真として見せていただきました。あなたの感性を生かされ、カラーであれモノクロであれ、生と死の作品を作り上げてください。
【評:平井純】
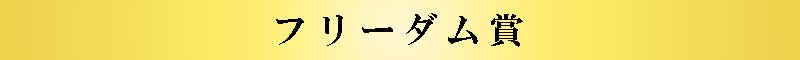

まず、これまで主催者が企画し実施して来ました、「托鉢」や「ベリーダンス」を予告なく「フリーダム賞」の対称に格上げしました。
理由ですが、これらの企画にもっと多くの皆様が参加して、その結果として応募にも反映して欲しいからです。
これまでも、これからも人脈を駆使して格安の価格で魅力ある企画を提供して行きます。自分の得意領域ではないとか、難しいとか言わずに新しい事に挑戦して下さい。そして、作品の幅を広げて欲しいと思っています。
昨年、私たちの思いを受け止めた方たちが、今年の「フリーダム賞」の対象になりました。賞の話になりますが、そのような経過もあり、主催者側の視点から選ばせて頂きました。
お寺での企画、それ自体珍しく貴重なベリーダンスになりました。石田さんの作品は「お寺とベリーダンス」の斬新さ、3名のダンサーの活き活きとした表情、ベリーダンスが醸し出す雰囲気を一番良くあらわしていました。
おそらく、将来「青梅フォトカジェー展」の歴史を振返る時、記録に残る作品になるでしょう。
【評:奥村よしひろ】
ひび割れた足の甲とつま先、太陽に晒された幾つものコンクリート状の塊の白と黒との写真とカラーの大樹の幹の肌とで構成されています。
作者は多分モノクロフィルムの光と影との経験があるのでしょうね。濃度の上がったフィルムを焼き付けたような強烈なコントラストであぶり出された二枚の白と黒とのモノクロの写真は(しわ)というタイトルを見事に表現し見るものの眼にざらざら、ごわごわと触れ五感で「しわ」に触れているようす。
カラー写真とモノクロ写真で組むことはよくあることですが、ここではカラーの写真が力負けをして、組み写真が少し緩んでしまいました。
さて、せっかくの足の写真が説明的です。思い切って画面いっぱいに足の甲と爪先だけを取り入れることで、足は足の属性から開放されて「しわ」としか言いようのないモノとしてのオーラさえ感じられる新しい世界が見えてきます。
また足に付いた虫は、せっかくのテーマを曖昧にしてしまっています。完成された作品ではありませんでしたが、未完を凌駕するだけの力を持った作品でした。何気ない、身近なものに作者の世界を発見し、表現なされる作者の眼と感性に敬服します。充分に写真展ができる内容のあるテーマですので腰を落ち着けて取り組んでみてください。
【評:平井純】
羽村の堰の多摩川で毎年行なわれる八雲神社の神事でしょう。
川を挟んで大勢の見物人やカメラマンが押し寄せるシチュエーション。
普通に撮ったのでは不必要な被写体が写り込んでしまう。作者はそれを嫌がり思い切ってドアップで切取った。それが成功しました。
川の中、神輿であること、廻りに白装束の沢山の担ぎ衆がいる事は、タイトルや画面からも容易に想像できます。
また、そっくりな二人の担ぎ衆の表情は力強さというより喜びの表情で、画面いっぱいに飛び散る水滴と相まって幻想性を高め、作品に昇華しました。
【評:奥村よしひろ】
この写真からはわからないのですが、新年の書初めを撮った写真のようです。冬休みの宿題でしょうか。兄妹がとてもいい表情をしています。
字を書くよりも顔に落書きしている方が楽しいですよね。実にイキイキとしていて楽しそうです。
「兄と妹(なにやってんだか)」というタイトルから、しょうもないなあという思いが感じられますが、きっと楽しいご家庭なんだろうなと想像できます。書初めは無事に終わったのかなあ。
【評:伊藤圭】
青梅の秋の風物詩と位置づけている托鉢です。今回からですが初めて組写真で見させて頂きました。
1枚目:町で偶然出会った托鉢の僧に嬉しさと喜びの表情の女性を見事に捉えています。バックに「青梅フォトカジェー展」のポスターを入れたのが憎い!
2枚目:単調で説明的、左右のバランスも気になりますが、組全体としてまとまっていて良かったです。
3枚目:道端の縁石に腰を下ろし編み笠を脱いで、足袋を直している僧侶の姿を逃さず美しく捉えています。
【評:奥村よしひろ】
暗闇に藤の花が浮かび上がり、幽玄という言葉がぴったりとくる作品です。
上から下に流れるように伸びている藤が、まるで水が落下する滝のようで、「フジの滝」とは言い得て妙です。光が上から降り注ぎ、下の方に届いていない様子が、山奥にひっそりと存在している滝を思い起させます。
タイトルが漢字で「藤」ではなく、カタカナの「フジ」と表現しているところに橋本さんの思いがありそうです。そこにはどんな思いが込められているのでしょうか。
【評:伊藤圭】

総 評
みなさまの写真を見せていただいた折の率直な感想です。今回はいままでと違った、気合の入った作品が寄せられました。
作品を大別しますと、外であれ、どこであれ、出会いをストレートに捉えたものと、いままでここでは見る機会の少なかったご自分の世界を内省的に創り上げた写真が見られました。
今、時代の流れの中で、写真もグルメ時代にはいり、そう毎度では飽きてしまい、しみじみと、うまいなぁ~っと、感嘆させてくれる写真が少ない気がします。そんな中で食材も身近にある、ごくありふれた中から、ご自分の眼で調達なされて、その方だけの人生の味わい深い物を作ってくださいました。
昨年、自分にとって写真はなんなのか、一年をかけてご自分に問うってくださいとお願いしましたが、そのご返事を頂いた気持ちでおります。 また、このコンテストを写真の鍛錬の道場のように意識され、連作の作品にきちんとタイトルをつけられ、目的意識をもたれて応募なされた方の姿勢にも心打たれました。風景の写真もよせられましたが色だけが際立って、作品の深さや厚みが無くなってしまい、見せかけだけのものになってしまい、もったいない作品もありました。
たとえ、不完全でも、真摯に被写体と向かい合い、そのかたの人生が投影された作品は見る方の心に響きます。賞のかたの講評にも書きましたが、ぜひ写真そのものが語りかけてくる作品を目指してください。そのためにも、また独りよがりにならないためにも、できるだけ写真を観ることです。むしろ嫌いな写真のほうがあなたに欠けた物を必ず補ってくれます。
最後に、写真をすることが楽しくて、楽しくて仕方ないような、あなたさまの日々を願います。
【平井純】